ポイント1:境界線が明確かどうかを確認する
結論:築古戸建を購入する前には、土地の境界線が明確かどうかを必ず確認しましょう。境界が曖昧なまま購入してしまうと、後々近隣住民とのトラブルに発展する可能性が高くなります。
理由:築古物件は、古くから存在しているため、現代の測量技術や登記制度が整備される前に建てられていることが多いです。そのため、土地の境界線が曖昧であるケースが少なくありません。
特に、境界杭(きょうかいくい)や塀などの目印がなかったり、近隣との取り決めが口約束で終わっていることもあり、どこまでが自分の土地なのかが分かりづらいのです。
このような状態で物件を購入してしまうと、隣地所有者と「ここは私の土地だ」といった争いが発生するリスクが生じます。境界問題は一度こじれると、解決までに時間もお金もかかるため、投資の収益性が著しく悪化してしまいます。
具体例:ある投資家が東京都郊外の築50年の戸建を購入しました。物件は相場より安く見えましたが、境界の確認を怠って購入してしまいました。
その結果、隣地の住民から「このフェンスはうちの敷地内に立てられている」とクレームを受け、結果的に撤去と損害賠償を求められる事態に。解決までに半年以上かかり、想定していた賃貸運用も遅れる結果となりました。
再主張:このようなトラブルを未然に防ぐためにも、購入前には必ず「境界確定図」や「筆界確認書」などの資料を確認し、不明な場合は土地家屋調査士による測量を依頼することを強くおすすめします。
ポイント2:越境物の有無をチェックする
結論:築古戸建を購入する際には、隣地からの越境物(屋根、塀、樹木の枝など)が存在しないかを確認しましょう。越境物は、将来的な撤去や損害補償の原因になりかねません。
理由:越境物とは、隣の家の構造物や植物などが、自分の敷地に入り込んでいる状態を指します。これがあると、所有権や管理責任の問題が発生するだけでなく、賃貸物件として貸し出す場合にも入居者からクレームが入る可能性があります。
また、越境物があることで、売却時に価格が下がったり、買い手が付きにくくなったりすることもあります。築古物件はただでさえ資産価値の変動が大きいため、こうしたリスクは避けておくべきです。
具体例:ある購入者が、庭に大きな木がある築古物件を購入しました。しかし購入後、その木の枝が隣家の敷地に大きくはみ出していることが判明。隣人から「剪定してほしい」と依頼が入り、定期的な管理と費用が発生。
さらに、強風で枝が折れて隣家の屋根を破損するトラブルも起き、損害賠償責任を問われました。
再主張:このようなリスクを避けるためにも、購入前の現地調査で「どこかから構造物や植物が越境していないか」をしっかり確認し、必要であれば測量士や不動産業者に相談することが重要です。
ポイント3:近隣住民との関係性を事前に把握する
結論:築古戸建を購入する際には、近隣住民との関係性や過去のトラブルがなかったかを事前に調査しましょう。良好な近隣関係は、スムーズな賃貸運営や物件管理において非常に重要です。
理由:築古物件があるエリアでは、昔から住んでいる住民が多く、地域のルールや慣習が根強く残っていることがあります。
新しく入ってきた所有者や賃借人に対して警戒心を持たれる場合も少なくありません。過去に所有者と近隣住民との間でトラブルがあった場合、新しい所有者にもその悪印象が引き継がれることがあります。
特に境界線に関するトラブルや、騒音、ゴミ出しマナーなど、日常生活に関する問題が起こっていた物件では、スムーズな賃貸運営が難しくなることも。
具体例:ある投資家が購入した築40年の戸建では、過去の所有者と隣家の住民との間でゴミ出しのルールを巡るトラブルがあったそうです。
新しい所有者が管理会社を通して入居者を募集したところ、近隣住民から「また変な人が入ってくるのか」と苦情が入り、入居希望者が見学時に不安を感じて申し込みを見送る事例がありました。
再主張:こうした問題を未然に防ぐために、物件の購入前に「近所の住民と話してみる」「不動産仲介業者にヒアリングする」などして、地域の雰囲気や過去のトラブルの有無を把握しておくことが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 境界トラブルを避けるためには何を確認すべきですか?
A. 境界確定図や筆界確認書があるか確認し、不明な場合は土地家屋調査士に測量を依頼することが大切です。
Q2. 越境物とは何ですか?
A. 隣の建物の屋根や塀、木の枝などが自分の敷地に入り込んでいる状態を指します。事前確認が重要です。
Q3. 近隣住民との関係はどう調べれば良いですか?
A. 不動産仲介業者へのヒアリングや、可能であれば近隣住民と直接話すことで、雰囲気や過去のトラブルを把握できます。


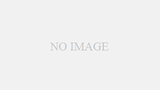
コメント