- 不動産投資をやるのにオススメのジャンルを知りたい・・・
- 色んなジャンルがあるけど、どれにすれがいいか分からない・・・
- 初心者にはコレがオススメ!というジャンルを教えて・・・!
不動産投資といってもジャンルがあります。マンション1棟、ワンルームマンション、アパート1棟、戸建て・・・・。
大きな金額を必要とする不動産投資で失敗してしまうと、一撃でノックアウトという状況に陥ってしまいます。

特に初心者の方は分からないまま勢いにまかせて購入して失敗するケースがありま・・・。
そこでこの記事では、不動産投資初心者向けに、「築古戸建不動産投資の基本となる情報」をまとめて解説します。
築古戸建投資を検討中のあなたは、今まさにこんな悩みを抱えているのではないでしょうか。
- 予期せぬ大きな修繕費や維持管理の費用への不安
- 物件の「見極め」や「判断」に関する不安
- 空き室リスクと収益性への不安
- 売却(出口戦略)への不安
実は、築古戸建投資で「失敗する人」と「年利20%超を実現する人」の違いは、メリット・デメリットを正しく理解しているかどうかです。
多くのブログでは「築古戸建は稼げる!」と言いますが、それは半分正解で半分間違いです。
この記事では、不動産投資経験を持つ筆者が、リアルな現実をお伝えします。
この記事を読めば、「築古戸建不動産投資はどういった投資なのか」が分かります。

「築古戸建投資って本当に儲かるの?それともリスクが高すぎる?」

「築古戸建投資のメリット・デメリットをしっかり理解すれば大丈夫」
✅ 築古戸建投資の3大メリット
💰 メリット1:初期費用が圧倒的に安い
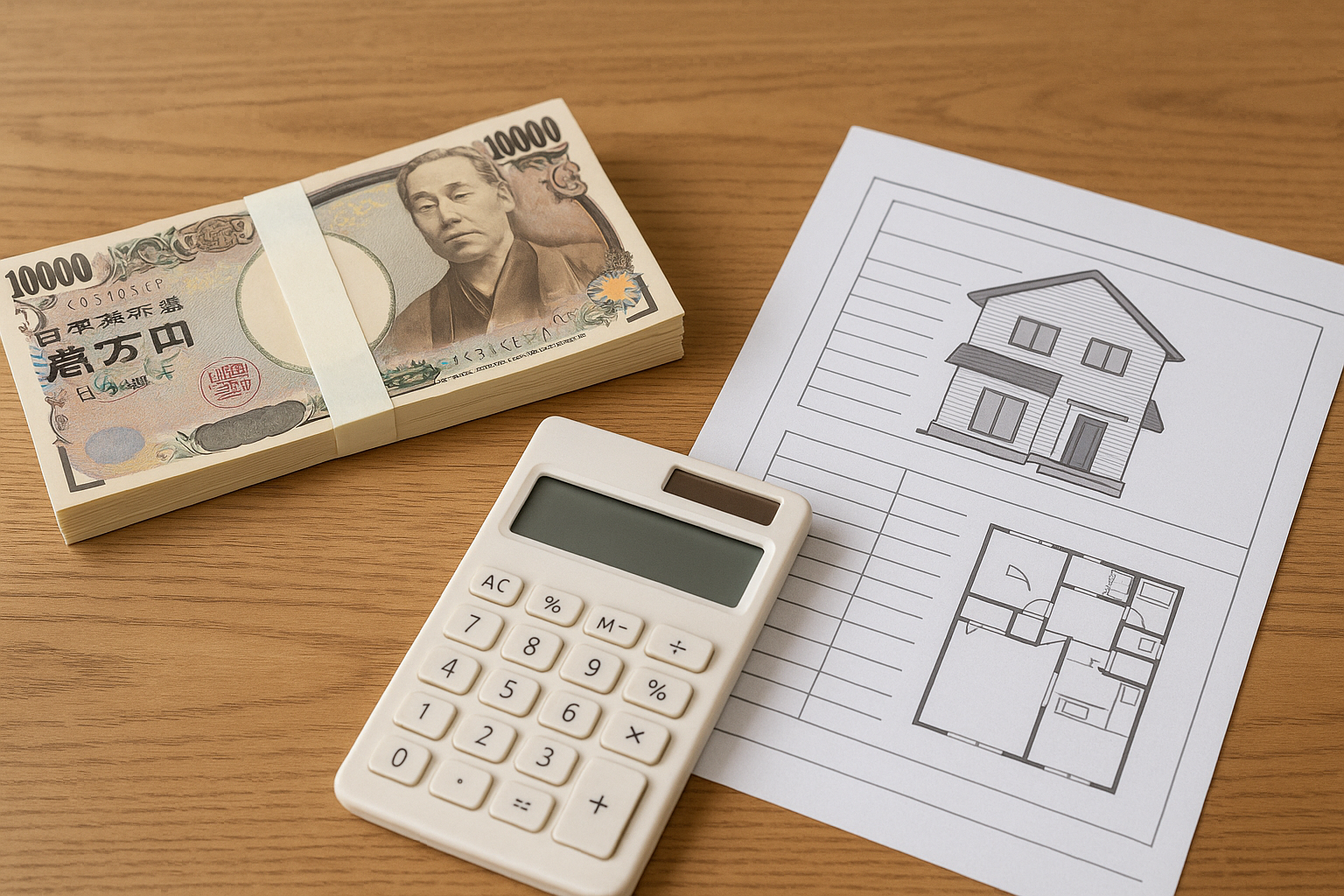
サラリーマンとして安定した収入を得ながら、将来に向けた資産形成を考えるなら、築古戸建投資は非常に魅力的な選択肢です。初期費用の安さは、他の投資手法と比べて圧倒的なアドバンテージがあります。
なぜ築古戸建投資の初期費用は驚くほど安いのか?
①物件価格そのものが安い
築古戸建投資の最大の魅力は、地方なら500万円前後から始められることです。これは新築マンション投資や区分マンション投資とは次元の違う安さです。
- 新築マンション(3,000万円):初期費用約1,050万円(頭金600万円+諸費用450万円)
- 築古戸建(500万円):初期費用約550万円(現金購入の場合)
この差は実に500万円!まさに桁が一つ違います。HOMES
②融資に頼らない現金購入のメリット
築古戸建投資では現金購入が主流で、これが初期費用を劇的に削減します:
融資を使わないことで削減される費用:
- ローン保証料:物件価格の1-2%
- 融資手数料:50-100万円程度
- 金利負担:年間数十万円
- 団体信用生命保険料:年間数万円
実際の成功事例: ある投資家の実績では、累計1,150万円で7戸を購入し、年間家賃収入500万円を達成。表面利回り約25%という驚異的な成果を上げています。健美家
③具体的な初期費用シミュレーション
築古戸建(500万円物件)の場合
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件価格 | 500万円 | 地方の築古戸建 |
| 仲介手数料 | 33万円 | 低廉な空家等の媒介の特例 |
| 登録免許税 | 10万円 | 土地・建物の所有権移転 |
| 不動産取得税 | 15万円 | 固定資産税評価額の3% |
| 司法書士報酬 | 10万円 | 登記手続き |
| 印紙代 | 1万円 | 売買契約書 |
| 合計 | 約569万円 |
新築マンション(3,000万円物件)の場合
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件価格 | 3,000万円 | 都市部の新築1R |
| 頭金(20%) | 600万円 | |
| 仲介手数料 | 105万円 | |
| ローン諸費用 | 150万円 | 保証料・手数料等 |
| 登録免許税 | 60万円 | |
| 不動産取得税 | 90万円 | |
| その他諸費用 | 45万円 | |
| 合計 | 約1,050万円 | 物件価格除く |
差額:481万円 – これだけあれば築古戸建がもう1戸買えます!
④初期費用が安いことの3大メリット
リスクの最小化
初期投資額が少ないということは、万が一失敗しても損失を限定できるということです。公務員という安定職業を持つとも さんにとって、この安心感は何物にも代えがたいでしょう。
早期回収の可能性
500万円の物件で年間60万円の家賃収入があれば、約8年で投資元本を回収できます。新築マンションでは15-20年かかることを考えると、圧倒的に早いキャッシュフロー改善が期待できます。
複数戸展開の容易性
1戸目の収益が安定すれば、その家賃収入を元手に2戸目、3戸目と展開していけます。新築マンションでは1戸で資金が枯渇しますが、築古戸建なら段階的な規模拡大が現実的です。
⑤さらに初期費用を抑える5つの戦略
DIYによるリフォーム費用削減
自分で簡単な修繕を行うことで、リフォーム費用を50-70%削減できます。週末の時間を有効活用し、建物に関する知識も同時に身につけられる一石二鳥の効果があります。
仲介手数料の交渉
売主直売の物件を狙うか、仲介業者と交渉することで仲介手数料を削減できる場合があります。
諸費用ローンの活用
物件価格は現金でも、諸費用部分だけローンを使うことで手出し現金を更に削減できます。
税務面の優遇措置活用
築古戸建は固定資産税が安く、減価償却による節税効果も期待できます。
エリア選定の工夫
人口減少地域でも、駅近や学校近くなど立地の良い物件を選べば、安価でも安定した賃貸需要が見込めます。
⑥注意すべきポイント
初期費用の安さは魅力的ですが、以下の点には注意が必要です:
隠れたコストの把握
- 修繕費:年間家賃の10-15%程度
- 火災保険料:築古木造は割高(年間5-6万円程度)
- 管理費:自主管理でも時間コストがかかる
収益性の確認
安いだけでなく、賃貸需要があるかをしっかり調査することが重要です。
⑦まとめ:築古戸建投資で始める資産形成
築古戸建投資の初期費用の安さは、不動産投資の入り口として理想的です。特にサラリーマンような安定した職業の方にとって、リスクを抑えながら不動産投資の経験を積める絶好の機会です。
500万円から始められる築古戸建投資で、まずは1戸目からスタートし、徐々に規模を拡大していく。これこそが、確実で持続可能な資産形成の道筋なのです。
将来を見据えた賢い選択として、築古戸建投資を検討してみてはいかがでしょうか。初期費用の安さという圧倒的なメリットを活かし、着実な資産形成の第一歩を踏み出しましょう!
📈 メリット2:利回りが高くなりやすい

サラリーマンとして安定した収入基盤を持ちながら、さらなる資産形成を考えるなら築古戸建投資の利回りの高さは見逃せません。なんと利回り20%、場合によっては25%超という驚異的な数字も実現可能です!
築古戸建投資の利回りはなぜ驚異的に高いのか?
① 利回り比較:圧倒的な数字の差
最新データから見る物件タイプ別利回りを比較してみましょう:
| 物件タイプ | 平均利回り | 理想利回り |
|---|---|---|
| 築古戸建 | 15-25% | 20%以上 |
| 新築マンション | 3-5% | 6% |
| 中古マンション | 5-8% | 7-8% |
| 新築アパート | 7-8% | 8% |
| 中古アパート | 8-10% | 9-10% |
この数字を見れば一目瞭然!築古戸建の利回りは他の投資手法を圧倒しています。東進
② 実例で証明される驚異的な収益性
成功事例1:利回り25%の実績
- 総投資額:約2,000万円(7戸)
- 年間家賃収入:500万円
- 表面利回り:25%
この実例は決して特別なケースではありません。適切な戦略と実行力があれば、再現可能な成果なのです。健美家
成功事例2:300万円物件で月5万円収入
- 物件価格:300万円
- 月額家賃:5万円
- 年間利回り:20%
③築古戸建の利回りが高くなる5つの理由
物件価格の圧倒的安さ
利回りの計算式を思い出してください: 利回り(%)= 年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100
築古戸建は分母(物件価格)が極端に安いため、同じ家賃でも利回りが跳ね上がります。
具体例:
- 築古戸建(400万円)で月7万円 → 利回り21%
- 新築マンション(3,000万円)で月10万円 → 利回り4%
家賃の下落が限定的
築古物件の家賃は既に底値圏にあることが多く、さらなる下落余地が限られています。一方で立地が良ければ、リノベーション効果で家賃アップも可能です。
賃貸戸建ての供給不足
戸建賃貸は圧倒的に供給が少ないため、相場よりも高めの家賃設定が可能です。ファミリー層からの需要は根強く、競合が少ない分野です。アットホーム
DIY効果による投資額圧縮
自分で簡単な改修を行うことで、実質的な投資額を大幅に削減できます。これにより利回りがさらに向上します。
減価償却効果
築古木造は4年で償却完了するため、大きな節税効果を得られ、実質利回りがさらに向上します。
④利回り別・投資回収期間の比較
築古戸建(利回り20%)vs 新築マンション(利回り4%)
| 項目 | 築古戸建 | 新築マンション |
|---|---|---|
| 投資額 | 500万円 | 3,000万円 |
| 年間収入 | 100万円 | 120万円 |
| 回収期間 | 5年 | 25年 |
| 10年後累計収入 | 1,000万円 | 1,200万円 |
| 投資効率 | 200% | 40% |
築古戸建ならわずか5年で投資元本を回収!新築マンションの5倍のスピードです。
⑤表面利回りと実質利回りの実例計算
築古戸建(500万円物件)の場合
【表面利回り】
- 物件価格:500万円
- 月額家賃:8万円
- 年間家賃:96万円
- 表面利回り:19.2%
【実質利回り】
- 年間家賃:96万円
- 年間経費:20万円(税金、保険、修繕積立)
- 純収入:76万円
- 実質利回り:15.2%
それでも実質利回り15.2%は、他の投資手法と比べて圧倒的な高さです!
⑥地域別・築古戸建利回りの傾向
高利回りエリアランキング
| 地域 | 平均利回り | 特徴 |
|---|---|---|
| 東北地方 | 12-25% | 物件価格が安く、賃貸需要も一定 |
| 信州・北陸 | 15-28% | 観光地需要、移住需要 |
| 中国・四国 | 12-20% | 地方都市の安定需要 |
| 九州・沖縄 | 10-18% | 気候の良さで移住需要 |
| 首都圏郊外 | 8-15% | アクセス良好、価格も手頃 |
地方でも利回り20%超は十分達成可能です!健美家レポート
⑦利回りを最大化する5つの戦略
仕入れ価格の最適化
- 競売物件の活用
- 任意売却物件の情報収集
- 相続関連物件の早期発見
- 売り急ぎ物件の積極的アプローチ
効率的なリノベーション
高ROI改修の優先順位:
- 水回り設備の部分交換(30-50万円)
- 壁紙・床材の刷新(20-30万円)
- 外観の美装(10-20万円)
- 照明・コンセントの現代化(5-10万円)
家賃設定の最適化
- 近隣相場の徹底調査
- ターゲット層に合わせた設備
- 初期キャンペーンでの早期満室
- 定期的な市場価格の見直し
管理コストの削減
- 自主管理の検討
- 一括管理による効率化
- 予防保全による修繕費削減
- 長期入居促進策
税務最適化
- 減価償却の最大活用
- 修繕費vs資本的支出の判断
- 青色申告による節税
- 法人化のタイミング検討
⑧高利回り物件を見極める10のチェックポイント
🔍 物件選定の黄金ルール
✅ 立地条件
- 1.駐車場確保可能
- 2.駅徒歩15分以内または車でのアクセス良好
- 3.小学校・中学校が近い
- 4.スーパー・コンビニが徒歩圏内
✅ 建物状況
- 5.構造的問題がない
- 6.雨漏り・シロアリ被害なし
- 7.給排水設備の状況確認
- 8.再建築可能
✅ 収益性
- 9. 想定家賃の妥当性
- 10. 将来の賃貸需要見込み
⑨注意すべき「高利回りの罠」
⚠️ 避けるべき物件の特徴
法的制約物件
- 再建築不可
- 容積率オーバー
- 接道不良
構造的問題物件
- 旧耐震基準(1981年以前)
- 基礎の重大な欠陥
- アスベスト使用建物
立地問題物件
- 極端な人口減少地域
- 産業の衰退地域
- 自然災害高リスク地域
⑩築古戸建投資の利回りシミュレーション
パターンA:保守的シナリオ(利回り15%)
| 項目 | 1年目 | 5年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 500万円 | – | – |
| 年間収入 | 75万円 | 70万円 | 65万円 |
| 累計収入 | 75万円 | 365万円 | 685万円 |
| 投資回収率 | 15% | 73% | 137% |
パターンB:積極的シナリオ(利回り22%)
| 項目 | 1年目 | 5年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 400万円 | – | – |
| 年間収入 | 88万円 | 85万円 | 80万円 |
| 累計収入 | 88万円 | 435万円 | 825万円 |
| 投資回収率 | 22% | 109% | 206% |
⑪サラリーマンに最適な築古戸建投資戦略
📋 3段階ステップアップ方式
Phase 1:学習期(1戸目)
- 投資額:300-500万円
- 目標利回り:15-18%
- 自己資金100%
- DIY中心の改修
Phase 2:拡大期(2-3戸目)
- 投資額:400-600万円/戸
- 目標利回り:18-22%
- 効率化の追求
- 管理ノウハウ確立
Phase 3:安定期(4戸目以降)
- 投資額:500-800万円/戸
- 目標利回り:20%以上
- システム化・外注化
- 複数戸運営の最適化
💡 サラリーマンならではのメリット活用
- 安定収入による信用力
- 平日の物件見学が可能
- 退職後の安定収入確保
- 給与所得との損益通算効果
⑫今始めるべき理由:市場環境の追い風
📈 2024-2025年の市場トレンド
- 中古戸建成約件数:**+52.0%**増加
- 中古戸建価格:**-2.5%**軟化
- 空き家数:約900万戸で過去最多
- 相続関連売却の増加
**今まさに「仕入れ時」**の市場環境が整っています!
⑬まとめ:築古戸建投資で実現する驚異の利回り
築古戸建投資の利回りの高さは、単なる数字のマジックではありません。物件価格の安さ、家賃の安定性、供給不足による競争優位という構造的な要因に支えられた、再現性の高い投資手法なのです。
重要ポイント:
- ✅ 利回り20-25%は十分達成可能
- ✅ 5年で投資元本回収の超高速回転
- ✅ 新築マンションの5倍の投資効率
- ✅ サラリーマンの安定性との相性抜群
- ✅ 今の市場環境は絶好の仕入れ時
🎨 メリット3:差別化しやすい

築古戸建投資には他の投資手法にはない圧倒的な差別化のしやすさというメリットがあります。この特徴を活かせば、競合物件を大きく引き離し、高い家賃と安定した入居率を同時に実現できるのです!
なぜ築古戸建は差別化が圧倒的にしやすいのか?
🎯 供給不足という追い風
賃貸戸建は圧倒的に供給が少ないのが現状です。特にファミリー向けの戸建賃貸は、東京23区で3DK以上の供給不足が7割超えという状況です。オーナーズスタイル
この供給不足により、少しの工夫で大きな差別化効果が生まれるのです。
① アパート・マンションとの決定的な違い
| 項目 | 築古戸建 | アパート・マンション |
|---|---|---|
| 改修自由度 | 完全自由 | 規約・構造制約あり |
| 個性表現 | 無限大 | 限定的 |
| ターゲット設定 | 特化可能 | 画一的になりがち |
| 競合数 | 少ない | 多数存在 |
| 差別化コスト | 低い | 高額になりがち |
② 戸建ならではの差別化ポテンシャル
アパートにはない特徴を活用できる:
- 庭・駐車場の自由活用
- 間取り変更の完全自由
- ペット飼育の制約なし
- 近隣騒音を気にしない生活
- DIY可能な住環境
差別化成功事例:家賃1.5倍アップの実績
実例1:相場の1.5倍で即決した物件
物件概要:
- 築72年の古民家(トイレなし物件を再生)
- 周辺相場:4-5万円
- 成約家賃:7.5万円(相場の1.5倍!)
- 募集期間:約1ヶ月
差別化ポイント:
- 庭に砂利敷きで美観向上
- パントリー&ランドリールーム造作
- 55インチテレビの壁掛け設置
- 古民家の雰囲気を活かした和モダン仕上げ
この物件は「古びた雰囲気と海が目の前というロケーション」がバッチリ合い、友達3人組のシェアハウス利用で即決となりました。健美家
実例2:築39年で家賃1.1万円アップ
適切なターゲット設定により、築39年の古い物件でも月額1.1万円の家賃アップを実現した事例もあります。常識を覆すターゲット設定が功を奏した結果です。
差別化の4大戦略
戦略1:コンセプト型賃貸の実現
特定のライフスタイルに特化した物件作り
🎯 人気コンセプト例:
- アウトドア愛好家向け:土間・薪ストーブ・アウトドア用品収納
- 在宅ワーク特化型:防音書斎・高速WiFi・WEB会議ブース
- ペット共生住宅:ドッグラン・ペット専用設備・防臭対策
- DIY可能住宅:工作室・工具収納・改装自由
- 和モダン住宅:古民家×現代設備のハイブリッド
戦略2:低コスト高効果の差別化テクニック
💰 投資10万円以下で実現できる差別化
庭・外構の活用(費用:3-5万円)
・砂利敷きで美観向上(400円/袋×約10袋)
・バーベキュースペース設置
・家庭菜園エリア造成
・子供用遊具設置
収納空間の造作(費用:5-8万円)
・デッドスペース活用の造作棚
・ウォークインクローゼット増設
・パントリー・ランドリールーム
・階段下収納の有効活用
設備のモダン化(費用:8-10万円)
・壁掛けテレビの設置
・LEDダウンライト導入
・ウォシュレット設置
・システムキッチンへのプチ改修
戦略3:ターゲット別差別化戦略
🔸 ファミリー層向け
- 安全性重視:角の丸い造作家具、滑り止め加工
- 収納充実:おもちゃ収納、ランドセル置き場
- 庭活用:砂場、ブランコ、家庭菜園スペース
🔸 単身・カップル向け
- おしゃれ重視:インダストリアル、北欧、古民家風
- 機能性:ワークスペース、大容量収納
- プライベート空間:個室感のある間取り
🔸 高齢者向け
- バリアフリー:手すり、段差解消、滑り止め
- 安心設計:見守りシステム、緊急通報装置
- メンテナンス性:掃除しやすい素材選択
戦略4:季節・地域特性を活かした差別化
🌸 地域特性活用例
・観光地エリア:民泊風の和風インテリア
・学園都市:学習スペース・自習室完備
・郊外住宅地:ガーデニング・駐車場充実
・古い町並み:歴史ある街並みに調和した外観
⏰ 季節対応差別化
春:新生活応援(家電・家具付き)
夏:熱中症対策(遮熱・冷房効率化)
秋:収穫祭(家庭菜園・食材保管)
冬:暖房効率(断熱・床暖房)
差別化の実践手順:90日完成プログラム
Phase 1:企画・設計(1-30日)
🔍 Step 1:競合調査(1-7日)
- 半径1km以内の賃貸物件チェック
- 家賃・設備・特徴の詳細分析
- 空室物件の弱点特定
🎯 Step 2:ターゲット設定(8-14日)
- 地域の人口構成分析
- ライフスタイル調査
- ニーズの絞り込み
📋 Step 3:コンセプト確定(15-21日)
- 差別化ポイントの明確化
- 予算配分の決定
- 工程スケジュール作成
💰 Step 4:資材調達(22-30日)
- 材料・設備の発注
- 工具レンタル手配
- 施工業者選定(必要に応じて)
Phase 2:実装・改修(31-75日)
🔧 優先順位別施工
- 構造・安全性(31-45日)
- 水回り・設備(46-60日)
- 内装・造作(61-70日)
- 外構・仕上げ(71-75日)
Phase 3:仕上げ・募集(76-90日)
📷 Step 1:写真撮影(76-80日)
- プロ並みの物件写真撮影
- 差別化ポイントの強調
- ライフスタイル提案写真
📢 Step 2:募集開始(81-90日)
- 差別化を活かした募集図面
- SNS・Web活用の情報発信
- 内覧時のプレゼンテーション
差別化による収益インパクト
① 家賃アップ効果の実例
| 差別化内容 | 投資額 | 家賃アップ | 回収期間 |
|---|---|---|---|
| 壁掛けテレビ | 10万円 | +3,000円/月 | 2.8年 |
| 造作収納 | 8万円 | +5,000円/月 | 1.3年 |
| 庭・外構整備 | 5万円 | +8,000円/月 | 0.6年 |
| コンセプト型改修 | 50万円 | +20,000円/月 | 2.1年 |
② 入居スピード向上効果
差別化物件の特徴:
- 平均募集期間:2-4週間短縮
- 内覧→申込率:通常の2-3倍
- 長期入居率:20-30%向上
差別化を成功させる7つの黄金ルール
✅ Rule 1:地域ニーズとのマッチング
独自性追求よりも、地域の実需要に合った差別化を優先する
✅ Rule 2:投資回収期間の明確化
2-3年以内で投資回収できる差別化に集中する
✅ Rule 3:メンテナンス性の確保
見た目重視よりも、長期維持しやすい素材・設備を選択する
✅ Rule 4:汎用性の保持
特化しすぎず、次の入居者にも対応できる柔軟性を残す
✅ Rule 5:安全性の確保
差別化のために建築基準法や安全性を犠牲にしない
✅ Rule 6:コストコントロール
差別化投資は物件価格の10-15%以内に抑制する
✅ Rule 7:継続的改善
入居者の声を聞き、定期的にアップデートを行う
避けるべき差別化の3つの罠
⚠️ 罠1:過度な個性化
❌ 特殊すぎるデザイン・設備
❌ 趣味に走りすぎた改修
❌ メンテナンス困難な素材⚠️ 罠2:ターゲット無視
❌ 地域ニーズと合わない設備
❌ 年齢層に適さない仕様
❌ ライフスタイル不一致⚠️ 罠3:コスト過剰
❌ 回収困難な高額投資
❌ 家賃に転嫁できない設備
❌ ROI無視の改修今後のトレンド:差別化の新潮流
① 2025年注目の差別化キーワード
環境配慮型住宅
- 太陽光発電・蓄電池
- 断熱性能向上
- 雨水利用システム
- 生分解性素材の活用
ワークライフ融合対応
- Web会議専用ブース
- 24時間対応ワークスペース
- 高速インターネット標準装備
- 配達ボックス・宅配ロッカー
②健康・ウェルネス重視
- 空気清浄・換気システム
- 自然素材の多用
- 運動・ストレッチスペース
- メンタルヘルス配慮設計
まとめ:差別化で築く競争優位
築古戸建投資における差別化のしやすさは、他の投資手法では得られない大きなアドバンテージです。
重要ポイント:
- 🎯 供給不足市場での圧倒的優位性
- 💡 低コスト高効果の差別化テクニック
- 🏆 家賃1.5倍アップも実現可能
- ⚡ 募集期間大幅短縮効果
- 🛡️ 長期入居による安定収益
築古物件は間取りやデザインが古い分、リフォームやDIYで独自性を出しやすいです。
⚠️ 築古戸建投資の3大デメリット・リスク
🔧 デメリット1:リフォーム・修繕費用がかかる

🔴 現実的なコスト負担
- 年間維持費:30-40万円
- 30年間の総修繕費:500-800万円
- 想定外費用による失敗率:約31%
📊 具体的な失敗事例
- 300万円購入+400万円リフォーム→月5万円収入の事例
- シロアリ被害で追加200万円発生
- 雨漏り修理から屋根全面工事への拡大
💰 リフォーム費用の詳細相場
- 水回りリフォーム:60-400万円
- 外壁・屋根工事:60-300万円
- フルリフォーム:800-1500万円
⚠️ 築古特有のリスク
- 構造的問題、設備劣化、害虫被害
- 解体後に判明する隠れた問題
- 法規制対応の追加コスト
主な修繕箇所と費用目安:
- 屋根修繕:50-150万円
- 配管工事:30-100万円
- 内装リフォーム:100-300万円
⚠️ 注意点: 費用を見誤ると利回りが大きく下がります
🏠 デメリット2:空室リスクがある

重要な注意事項:築古戸建投資において、空室リスクは修繕費用と並んで最も深刻な問題です。高利回りの魅力に惑わされず、現実的なリスクを十分に理解することが重要です。
①空室リスクが築古戸建投資の最大の脅威である理由
築古戸建投資において、空室リスクは単なる「一時的な収入減少」ではありません。それは投資全体の収益性を根本から覆す可能性のある深刻な問題です。
新築マンションや築浅物件と異なり、築古戸建は以下の理由で空室リスクが格段に高くなります:
- 設備の古さや使い勝手の悪さによる入居者敬遠
- 限定的なターゲット層(低所得者層への依存)
- 競合物件との差別化の困難さ
- 立地条件の制約(駅から遠い、利便性が低いなど)
②築古戸建の空室率の現実
全国平均データ
築古戸建(築30年以上)の空室率
- 全国平均:15-25%
- 都市部:12-18%
- 地方部:20-35%
- 過疎地域:30%超
築年数別空室率
| 築年数 | 空室率 | 平均空室期間 |
|---|---|---|
| 築10年未満 | 8-12% | 1-2ヶ月 |
| 築10-20年 | 10-15% | 2-3ヶ月 |
| 築20-30年 | 12-20% | 3-4ヶ月 |
| 築30年以上 | 15-25% | 3-6ヶ月 |
| 築40年以上 | 20-35% | 6ヶ月以上 |
地域格差の実態
築古戸建の空室率は地域によって大きく異なります。特に人口減少が進む地方都市では、30%を超える高い空室率が記録されています。
③長期空室の具体的事例
6ヶ月以上空室の事例
事例:埼玉県某市の築35年戸建
- 購入価格:450万円
- 想定家賃:月6万円
- 実際の空室期間:8ヶ月(年間)
- 実質稼働率:33%
- 年間家賃収入:24万円(想定72万円)
- 実質利回り:5.3%(想定16.0%)
1年以上空室になった物件の特徴
長期空室物件に共通する特徴:
- 最寄り駅から徒歩20分以上
- 水回り設備の老朽化が深刻
- 間取りが現代のライフスタイルに合わない
- 周辺環境の治安や利便性に問題
- 競合物件が多数存在
実際の損失計算
月額家賃5万円物件での空室損失
- 3ヶ月空室:15万円の損失
- 6ヶ月空室:30万円の損失
- 1年空室:60万円の損失
- 1年半空室:90万円の損失
※固定費(税金、保険、管理費等)は空室期間中も発生
④ターゲット層の問題
築古戸建を借りる層の限定性
築古戸建の賃貸需要は極めて限定的です。主なターゲット層は以下に限られます:
- 低所得の単身者(フリーター、非正規雇用者)
- 高齢者(年金生活者)
- 外国人労働者
- ペット飼育者
- 生活保護受給者
単身者向けの需要減少
近年、単身者の賃貸ニーズは大きく変化しています:
- 築浅マンションの家賃下落により選択肢が拡大
- 在宅勤務普及による居住環境への要求レベル向上
- セキュリティ面での不安(一戸建ての場合)
ファミリー層のニーズとのミスマッチ
ファミリー層は築古戸建に対して以下の懸念を持っています:
- 子育て環境としての安全性への不安
- 学校区や教育環境の重視
- 住宅購入への志向(賃貸ではなく持ち家)
- 現代的な設備や間取りへの要求
⑤地域・立地による空室リスクの違い
都市部vs地方の空室率比較
| 地域分類 | 空室率 | 平均空室期間 | 家賃下落率(年) |
|---|---|---|---|
| 首都圏 | 12-18% | 2-4ヶ月 | 2-3% |
| 地方中核都市 | 18-25% | 4-6ヶ月 | 3-4% |
| 地方都市 | 25-35% | 6-12ヶ月 | 4-5% |
| 過疎地域 | 30%超 | 12ヶ月以上 | 5%以上 |
駅距離による影響
最寄り駅からの距離は空室リスクに決定的な影響を与えます:
- 徒歩10分以内:基準
- 徒歩15分:空室期間1.3倍
- 徒歩20分:空室期間1.8倍
- 徒歩25分以上:空室期間3倍以上
⑥人口減少地域のリスク
人口減少地域での投資リスク
人口減少率が年1%を超える地域では、賃貸需要の継続的な減少により、空室率が年々上昇する傾向があります。一度空室になると1年以上埋まらないケースが多発しています。
⑦経済的損失の詳細計算
月額家賃5万円物件での損失シミュレーション
物件概要
- 購入価格:300万円
- 想定月額家賃:5万円
- 年間想定収入:60万円
- 固定費(年間):15万円(税金、保険、管理費等)
空室期間別の損失計算
| 空室期間 | 家賃損失 | 固定費負担 | 合計損失 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月(満室) | 0万円 | 15万円 | -15万円 | 15.0% |
| 3ヶ月 | 15万円 | 15万円 | -30万円 | 10.0% |
| 6ヶ月 | 30万円 | 15万円 | -45万円 | 5.0% |
| 9ヶ月 | 45万円 | 15万円 | -60万円 | 0% |
| 12ヶ月 | 60万円 | 15万円 | -75万円 | -5.0% |
機会損失の考え方
空室による損失は家賃収入の減少だけではありません:
- 銀行預金との機会損失(年0.1%として)
- 他の投資商品との比較損失
- 物件価値の継続的な下落
- 時間的コストの損失
⑧空室対策の現実と限界
家賃下げの効果と限界
家賃を下げることで空室期間を短縮できる場合がありますが、限界があります:
家賃下げの効果
- 10%下落:空室期間30%短縮
- 20%下落:空室期間50%短縮
- 30%下落:空室期間70%短縮
※ただし、一度下げた家賃を上げることは困難
リフォーム投資の費用対効果
空室対策のリフォームは効果が限定的です:
- 水回りリフォーム(80万円):家賃上昇5,000円/月
- 内装全面リノベ(150万円):家賃上昇8,000円/月
- 投資回収期間:10-15年
- 空室期間短縮効果:限定的
管理会社変更の効果
管理会社を変更しても根本的な解決にはならないケースが多数:
- 物件の基本的魅力は変わらない
- 立地条件は改善できない
- 競合環境は変化しない
- 家賃相場は市場が決定
⑨失敗事例の詳細分析
購入価格300万円、年間空室期間8ヶ月の事例
栃木某市の築40年戸建投資の失敗事例
投資計画(当初)
- 購入価格:300万円
- リフォーム費用:100万円
- 総投資額:400万円
- 想定家賃:月5.5万円
- 想定年間収入:66万円
- 想定利回り:16.5%
実際の結果(3年平均)
- 平均空室期間:年8ヶ月
- 稼働率:33%
- 実際の年間収入:22万円
- 年間固定費:12万円
- 年間純収入:10万円
- 実質利回り:2.5%
失敗要因
- 最寄り駅から徒歩25分の立地
- 周辺の競合物件増加
- 人口減少による需要減退
- 築年数による敬遠
地方物件での2年連続空室事例
青森県某市の築45年戸建投資の失敗事例
物件概要
- 購入価格:180万円
- 想定家賃:月4万円
- 購入後2年間完全空室
- 累積損失:120万円(家賃損失96万円+固定費24万円)
対策と結果
- 家賃を3万円に下げても入居者なし
- 50万円のリフォーム実施も効果なし
- 管理会社を3回変更するも変化なし
- 最終的に100万円で売却(80万円の損失)
⑩まとめ:空室リスクを踏まえた投資判断の重要性
築古戸建投資における空室リスクは、単なる「一時的な収入減少」ではなく、投資全体の成否を左右する決定的な要因です。以下の点を十分に理解した上で投資判断を行う必要があります。
投資前に必ず検討すべき空室リスク要因
- 対象地域の人口動態と賃貸需要の将来予測
- 競合物件の状況と差別化の可能性
- 最寄り駅からの距離と交通利便性
- ターゲット層の特定と需要の安定性
- 家賃下落リスクと投資収益への影響
現実的な投資判断のポイント
- 保守的な稼働率で計算:80%程度での収益シミュレーション
- 家賃下落を織り込む:年2-3%の家賃下落を想定
- 出口戦略の検討:売却時の価格下落リスク
- 地域の将来性:人口減少地域は避ける
- 複数物件での分散:単一物件依存の回避
高利回りの魅力に惑わされることなく、空室リスクを現実的に評価し、長期的な投資戦略を構築することが成功の鍵となります。特に公務員のような安定収入がある方こそ、リスクを正確に把握し、慎重な投資判断を行うことが重要です。
最終チェックポイント
投資を検討している築古戸建について、以下の質問に「はい」と答えられない場合は、投資を見送ることを強く推奨します:
- 年間6ヶ月の空室期間でも投資として成立するか?
- 家賃が20%下落しても投資として成立するか?
- 3年後も同じ賃貸需要が期待できるか?
- 売却時に投資額の50%以上で売れる見込みはあるか?
空室リスクが高い立地:
- 駅から遠い(徒歩15分以上)
- 人口減少が進む地方
- 周辺に商業施設がない
対策: 事前の需要調査が必須
🏦 デメリット3:融資が通りにくい場合がある
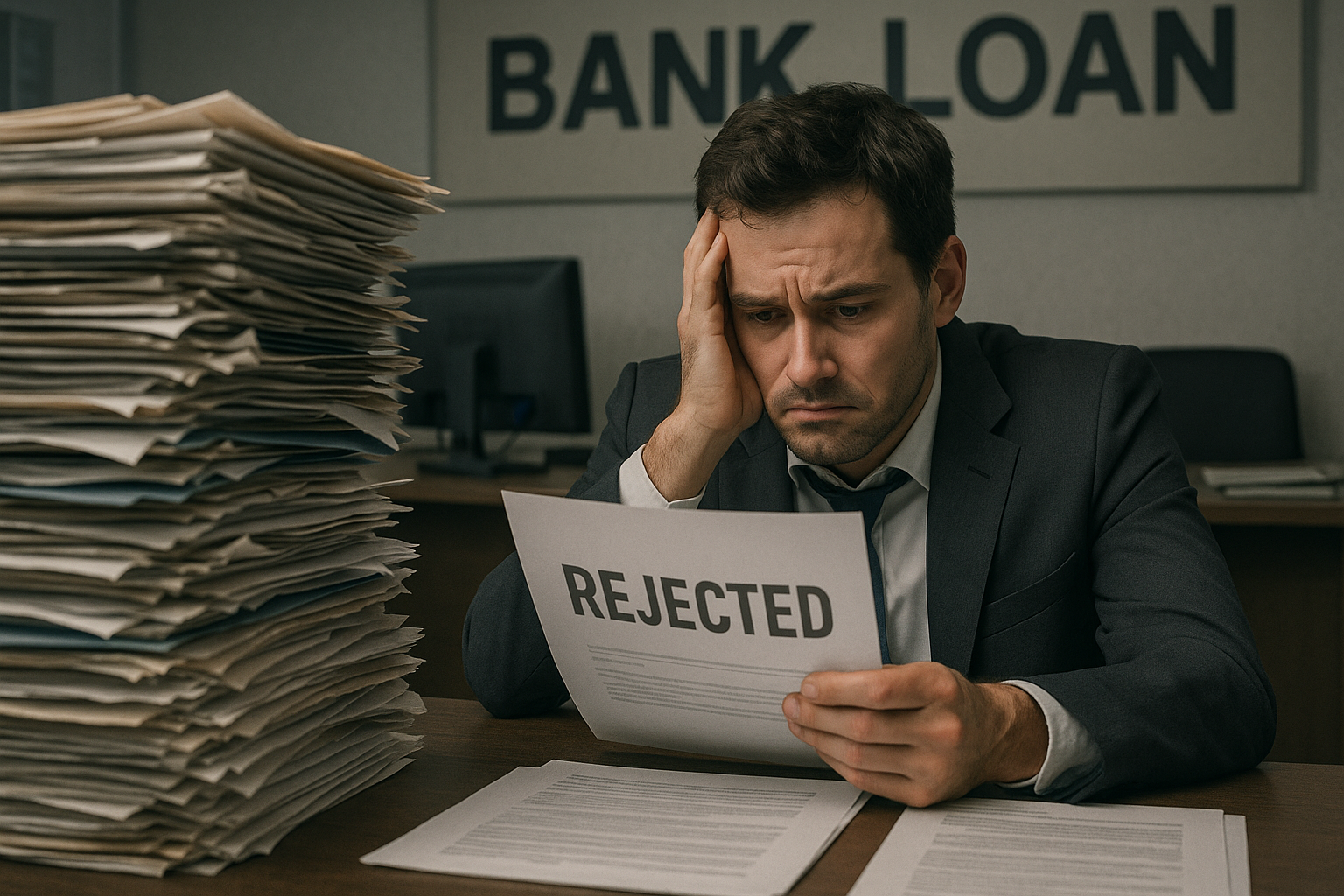
築古戸建投資は魅力的な投資手法として注目されていますが、最も大きな障壁となるのが「融資の難しさ」です。2025年現在、金融機関の融資姿勢はますます厳格化しており、築古戸建投資家にとって資金調達は重要な課題となっています。本記事では、築古戸建投資で融資が通りにくい理由と、その具体的なデメリットを徹底解説します。
①法定耐用年数という避けられない壁
木造戸建の耐用年数の実態
築古戸建投資で最初に直面するのが、法定耐用年数22年という制約です。木造住宅の場合、新築から22年を経過すると、多くの金融機関では融資対象外となってしまいます。
BONZ不動産の2025年最新レポートによると、「今から不動産投資を始める人にとっては非常に厳しい状況で、一部の金融機関を除いて、ほとんどの金融機関は事業実績の無い人には融資をしない」とされています。
融資期間の短縮による返済負担増
築古物件では残存耐用年数が短いため、融資期間も大幅に短縮されます。具体例を見てみましょう:
| 物件種別 | 融資期間 | 借入額3,000万円・金利2%の場合の月返済額 |
|---|---|---|
| 新築戸建 | 35年 | 約10万円 |
| 築20年戸建 | 15年程度 | 約19万円 |
| 築25年超戸建 | 10年程度 | 約28万円 |
このように、築年数が古くなるほど月々の返済負担が重くなり、キャッシュフローが悪化するリスクが高まります。
②担保評価の厳格化
建物価値のゼロ評価
多くの金融機関では、築20年を超えた木造戸建の建物部分を担保価値ゼロとして評価します。これは、法定耐用年数を基準とした機械的な評価によるものです。
SBI新生銀行の住宅ローンコラムでは、「木造住宅の法定耐用年数は22年のため、築古建物が築浅物件よりも担保評価が低くなる」と明確に述べられています。
土地評価への依存
築古戸建では建物評価が期待できないため、土地の価値のみで融資判断されることが一般的です。しかし、地方や郊外の物件では土地価格も低く、十分な担保価値を確保できないケースが多発しています。
③金融機関別の融資姿勢の違い
メガバンクの厳格な基準
メガバンクは法定耐用年数に対して最も厳格で、原則として耐用年数を超えた築古戸建への融資は行いません。不動産投資情報サイトによると、「特にメガバンクはこの基準に厳しく、耐用年数を超えた融資は原則受け付けていない」とされています。
地方銀行・信用金庫の柔軟性
一方で、地方銀行や信用金庫の中には、以下のような独自基準を設けている金融機関もあります:
- 60年ルール: 築年数に関係なく、「60年-築年数」まで融資する
- 収益重視評価: 物件の収益力を重視した審査
- エリア特化評価: 地域の実情に合わせた柔軟な担保評価
ただし、これらの金融機関でも審査は厳格化の傾向にあり、2025年の融資情勢では「既存借入が少ない不動産投資1~2棟目の方にオススメ」という条件付きとなっています。
④2025年の追加課題:建築基準法改正の影響
4号特例の縮小・廃止
2025年4月に施行された建築基準法改正により、従来の「4号特例」が実質的に廃止されました。建築業界レポートによると、「これまで一部建築審査が省略できた『4号特例』が縮小され、実質的に廃止される」とされています。
この影響で、築古戸建の構造や安全性に関する審査がより厳格化し、融資審査においても以下の影響が予想されます:
- 建築確認書類の不備による融資謝絶の増加
- 耐震診断書の必要性の高まり
- 適法性確認のための追加コストの発生
⑤属性による制約の厳格化
年収・勤続年数の要件
築古戸建投資では、物件の担保価値が低いため、借主の属性がより重要になります。一般的な要件は以下の通りです:
| 項目 | 一般的な基準 | 築古戸建の場合 |
|---|---|---|
| 年収 | 500万円以上 | 700万円以上 |
| 勤続年数 | 2年以上 | 3年以上 |
| 自己資金 | 1-2割 | 3-4割 |
| 金利 | 1.5-2.5% | 2.5-4.0% |
事業実績の重要性
不動産投資融資の最新動向では、「ほとんどの金融機関は事業実績の無い人には融資をしない」と指摘されており、築古戸建投資では特に以下の実績が求められます:
- 不動産投資の経験年数
- 既存物件の運営実績
- 安定した家賃収入の履歴
⑥金利上昇による追加負担
2025年の金利動向
2025年現在、金利は上昇傾向にあり、築古戸建投資にとってさらなる逆風となっています。築古アパート投資レポートによると、「2025年現在、金利は上昇傾向にあり、金融機関の融資姿勢はより慎重になっている」とされています。
リスクプレミアムの上乗せ
築古戸建では、以下のリスクプレミアムが金利に上乗せされる傾向があります:
- 築年数リスク: +0.5-1.0%
- 空室リスク: +0.3-0.8%
- 修繕リスク: +0.2-0.5%
- 流動性リスク: +0.3-0.7%
⑦対策と今後の展望
現実的な対応策
築古戸建投資で融資を受けるための現実的な対策として:
- 自己資金比率の向上: 最低でも物件価格の30-40%の自己資金準備
- 属性の改善: 年収・勤続年数・資産状況の向上
- 実績の蓄積: 小規模物件からの段階的な投資拡大
- 金融機関の選択: 地方銀行・信用金庫への重点的なアプローチ
代替資金調達手段の検討
従来の銀行融資以外の選択肢として:
- ノンバンクローン: 金利は高めだが審査は柔軟
- 不動産担保ローン: 既存不動産を活用した資金調達
- クラウドファンディング: 小口投資による資金集め
- 共同投資: パートナーとの資金出し合い
⑧まとめ
築古戸建投資における融資の難しさは、法定耐用年数、担保評価、金融機関の審査基準など多面的な要因によるものです。2025年現在、これらの制約はさらに厳格化しており、投資家にとって大きなハードルとなっています。
しかし、適切な戦略と準備があれば、築古戸建投資での融資獲得は不可能ではありません。重要なのは、金融機関の立場を理解し、リスクを最小化する具体的な計画を提示することです。
今後築古戸建投資を検討される際は、融資の困難さを十分に認識した上で、綿密な資金計画と代替手段の検討を行うことをお勧めします。市場環境は厳しさを増していますが、だからこそ適切な準備と戦略が成功への鍵となるのです。
📋 築古戸建投資の成功チェックリスト
投資前に必ずチェック:
- ☐ 立地の需要調査完了
- ☐ リフォーム費用の詳細見積取得
- ☐ 融資可能性の確認
- ☐ 賃料相場の調査完了
- ☐ 利回り計算の実施
まとめ:築古戸建投資で成功するために
築古戸建投資は、少額から始められる点と高利回りが狙える点が大きな魅力です。
一方で、修繕費用や空室リスクといったデメリットも存在するため、正しく理解した上で取り組むことが成功のカギになります。
🚀 次のステップ
投資を具体的に検討されている方は、以下の記事で実践的な始め方をチェックしてみてください:
👉 「築古戸建投資の始め方|5ステップでわかる初心者ロードマップ」
関連記事:
- 「築古戸建の物件選びで失敗しない5つのポイント」
- 「築古戸建リフォーム費用を抑える実践テクニック」

コメント